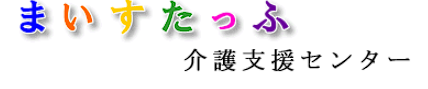重要事項説明書 (居宅介護支援事業)
事業者: (株)まいすたっふ介護支援センター
1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電話: (042-443-7871) (受付時間: 月~金曜日 8:30~17:30)
担当: 介護支援専門員 豊田 幸穂 / 管理責任者 豊田 幸穂
2. 居宅介護支援事業所の概要
(1) 居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
| 事業所名 | (株)まいすたっふ介護支援センター |
|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市多摩川1-3-1センチュリー調布1階 |
| 事業所の指定番号 | 居宅介護支援事業 (東京都 第1374201810号) |
| サービスを提供する実施地域 | 調布市・府中市・その他 |
(2) 事業所の職員体制
管理者 1名 介護支援専門員 2名
(3) 営業時間
月~金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
(土・日曜・祝日・12月31日~1月3日は休業)
(4) 事業計画及び財務内容について
事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
3. 居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ
付属別紙1・2を参照
4. 利用料金
(1) 利用料(ケアプラン作成料)
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
(居宅介護支援利用料)
- (1) 介護支援専門員取扱件数40件未満の場合
要介護1・2 12,076円 / 要介護3・4・5 15,690円 - (2) 介護支援専門員取扱件数40件以上60件未満の場合
要介護1・2 ___円 / 要介護3・4・5 ___円 - (3) 介護支援専門員取扱件数60件以上の場合
要介護1・2 ___円 / 要介護3・4・5 ___円 - (エ) 初回加算 3,316円
- (オ) 通院時情報連携加算 (利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合) 5,560円
- (カ) 入院時情報連携加算Ⅰ 2,780円 / 入院時情報連携加算Ⅱ 2,224円
- (キ) ターミナルマネジメント加算 (「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行う) 1か月につき 4,448円
- (ク) 緊急時居宅カンファレンス加算 1か月につき2,224円
- (ケ) 退院退所加算Ⅰ ① (病院等の職員から利用者の情報をカンファレンス以外の方法により1回 受けている場合) 5,004円
- (コ) 退院退所加算Ⅰ ② (病院等の職員から利用者の情報をカンファレンスにより1回うけている場合) 6,672円
※尚、上記各料金は介護保険サービス計画に対し、介護保険制度から保険給付されますので、ご利用者様のご負担はございません。
(2) 交通費
前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。
(3) 解約料
ご利用者様はいつでも契約を解約することができ、いっさい料金はかかりません。
5. サービス割合の説明
当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙3(居宅サービスへ位置付けたサービスのうち訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与が占める割合等について)のとおりである。
6. 公正中立なケアマネジメントの確保
利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求める事ができる。又、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能である。
7. サービス内容に関する苦情
(1) 当事業所の相談・苦情窓口
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。
(2) その他の窓口
※調布市役所 福祉健康部高齢者支援室介護給付係
電話番号 042-481-7321 (受付時間: 8:30~17:15 土日祝を除く)
※東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口
東京都千代田区3-5-1 東京区政会館11階
電話番号 03-6238-0177 (直通、受付時間: 9:00~17:00土日祝を除く)
8. 事故発生時の対応
介護支援専門員は、居宅介護支援を実施中に利用者の病状が急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに利用者のご家族・主治医に連絡する等の措置を講ずると共に管理責任者に報告いたします。
9. 個人情報の使用等及び秘密の保持
(1) 株式会社まいすたっふ及び法人の職員は、利用者及びその家族の個人情報を下記による必要最小限の範囲で使用、提供又は収集(以下「使用等」とします。)させて頂きます。
- ① 利用者に関わる居宅サービス計画の立案、作成及び変更に必要な場合。
- ② サービス担当者会議、その他介護支援専門員とサービス事業所との情報共有及び連絡調整等に必要な場合。
- ③ 利用者が医療サービスを希望され、主治医の意見を求める必要のある場合。
- ④ 利用者の状態の変化に伴い、親族、医療機関及び公共行政機関等に緊急を要する場合。
- ⑤ 介護保険にかかる行政指導、調査を受ける場合。
- ⑥ サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関による調査を受ける場合。
(2) 使用等が必要な個人情報が記載された書類は次のとおりです。
- ① 介護保険被保険者証・介護保険負担割合証・医療受給者証・身体障害者手帳。
- ② アセスメント書類。
- ③ 居宅サービス計画書。
- ④ 支援経過記録。
- ⑤ 主治医の意見書・診断書。
- ⑥ 減額証。
- ⑦ サービス実施記録。
- ⑧ 介護認定にかかる調査内容・介護認定審査会による判定結果・意見及び主治医意見書
10. オンラインツール等を活用した会議の開催
ご利用者又はご家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取り扱いに留意する。
11. 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
(1) 基本的な考え方(目的)
感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応等を事業所における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い介護サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程及び社会的規範を遵守するとともに、当社における適正な感染対策の取り組みを行う。
(2) 感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応等の整備
※平常時の対策
- ①「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に取り組む。
- ② 職員の清潔保持及び健康状態の管理に努め、特に従事者が感染源となることを予防し、利用者及び従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」を整備する。又、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。
1) 利用者の健康管理
2) 職員の健康管理
3) 標準的な感染予防策
4) 衛生管理 - ③ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員や委託業者を対象に年2回の「研修」を定期的に実施する。
- ④ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年2回の「訓練」を定期的に実施する。
- ⑤ 感染対策委員会を中心に感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ出し、定期的に指針を見直し「指針の更新」を行う。
※発生時の対応
- ① 日常の業務に関して感染事例または感染おそれのある事例が発生した場合には、「感染対策マニュアルや業務継続計画(BCP)」に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。
- ② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。
1) 生活空間・動線の区分け
2) 消毒
3) ケアの実施内容・実施方法の確認
4) 濃厚接触者への対応 など - ③ 感染事例等が発生後は、必要に応じて管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「関係者への連絡」を速やかに行う。
イ) 社内: 役職・管理者
ロ) 利用者家族: 氏名・連絡先 など
<変更・廃止手続き>
本方針の変更及び廃止は、感染症対策委員会の決議により行う。
<附則>
本方針は、2025年6月25日から適用する。
12. 高齢者虐待防止のための指針
(1) 基本方針
利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待のための措置を確実に実施するために本方針を定める。
(2) 高齢者虐待の定義
- ① 身体的虐待
高齢者お身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 - ② 介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 - ③ 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 - ④ 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 - ⑤ 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することとその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
(3) 虐待防止のための具体策措置
- ① 苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情にについて真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。 - ② 虐待防止検討委員会の設置
1、事業所は、虐待発生の防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
2、委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
3、委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
4、委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
ア、虐待防止のための職員研修の内容等に関すること
イ、虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
ウ、職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
エ、虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
オ、再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること - ③ 職員研修の実施
1、職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
2、具体的には、次のプログラムにより実施する。
ア、高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ、高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ、虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ、早期発見・事実確認と報告等の手順
オ、発生した場合の改善策
3、研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
4、研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する。 - ④ その他の取り組み
1、提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
2、職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
3、本指針等の定期的な見直しと周知
(4) 職員の責務
職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに区市町村へ報告しなければならない。
(5) 指針の閲覧
「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
13. 勤務体制の確保(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇)の確保
- ① 男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策に取り組む。
- ② 適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
14. 業務継続計画(BCP)の策定等
感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じる。
15. 当法人の概要
| 法人種別・名称 | 株式会社 まいすたっふ |
|---|---|
| 資本金 | 4,000,000円(資本準備金含まず) |
| 社員数 | 5名(正社員のみ) |
| 設立 | 平成19年11月26日 |
| 所在地・電話 | 東京都調布市多摩川1-3-1センチュリー調布1階 042-443-7871 |
| 代表取締役 | 豊田 幸穂 |
| 事業内容 | 居宅介護支援事業 地域密着型通所介護 |
付属別紙
(付属別紙1) 要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。
1. 提供する居宅介護支援について
- ・ 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
- ・ 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
- ・ 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2. 要介護認定後の契約の継続について
・ 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
3. 要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について
要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。
4. 注意事項
要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。
- (1) 要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。
- (2) 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。
(付属別紙2) サービス提供の標準的な流れ
- 居宅サービス計画作成等サービス利用申込み
- 当社に関すること居宅サービス計画作成の手順、サービスの内容に関して大切な説明を行います
- 居宅サービス計画等に関する契約締結
※ご利用者は区役所へ【居宅サービス計画作成依頼届出書】の提出を行っていただきます。(提出代行は可能) - ケアマネジャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します
- 地域のサービス提供事業者の内容や、料金等をお伝えし、利用するサービスを選んでいただきます
- 提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します
- 計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利用の調整を行います
- 居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行います
- サービス利用
- 利用者やご家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提供事業者と連絡調整を行います
- 毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します
- 利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサービスの実施状況の把握を行います。
- 居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。
(付属別紙3) 【当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合】
① 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
| 訪問介護 | % |
| 通所介護 | % |
| 地域密着型通所介護 | % |
| 福祉用具貸与 | % |
② 前6ヵ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービス毎の、同一事業者によって提供されたものの割合
| 訪問介護 | ① % |
|---|---|
| ② % | |
| ③ % | |
| 通所介護 | ① % |
| ② % | |
| ③ % | |
| 地域密着型介護 | ① % |
| ② % | |
| ③ % | |
| 福祉用具貸与 | ① % |
| ② % | |
| ③ % |
※判定機関 令和7年度
□前期(3月1日~8月末日) □後期(9月1日~2月末日)